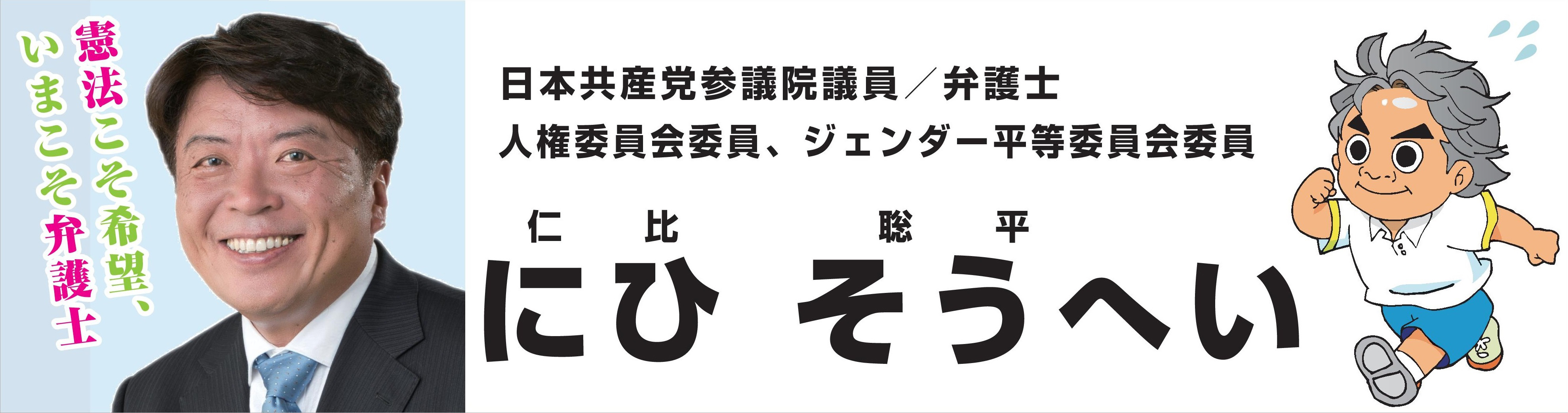○参考人(小木曽綾君) おはようございます。中央大学の小木曽と申します。
法科大学院で刑事訴訟法を担当しておりますほか、本法案に係る法制審議会の部会で委員を務めておりました。この法案に賛成の立場から意見を申し上げます。
法案には第一から第四までございますが、その一は、著しく長期又は多数回にわたる事件を裁判員対象事件から除外するというものであります。
裁判員制度の理念は、法の一条に、国民の裁判への参加が司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すると説明されております。したがって、これは、裁判を受ける被告人の権利とか参加する国民の権利というわけではなくて、刑事裁判についての国民の理解と信頼の向上に資するということがその目的ということでありますので、仮に余りに国民の負担が重くなるということが想定された場合、なりわいを犠牲にしてでも裁判への理解と信頼を確保するために裁判員として務めを果たせというわけにはいかないだろう、それを強いれば、かえって国民の司法制度への信頼を損なうおそれがあるのではないかというのがこの提案を支える理由であると理解しております。
また、仮に裁判員がいなくなってしまいますと、次の裁判員を選任する間、裁判手続が停止することになりまして、これは被告人の迅速な裁判を受ける権利を侵しかねません。法案は、憲法及び裁判員制度の理念と矛盾しないものと思います。
次に、その対象をどのように定めているかということですが、一つは、裁判手続が始まる前に、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたる、又は公判期日等が著しく多数にわたることを回避できない、そのときに、他事件の選任、解任の状況や、その事件での選任手続の経過等を考慮して決める、又は、裁判が始まってから後で同様の事情がある場合にこれを除外するということになっておりまして、対象事件が具体的に定められてはおりません。
そうすると、本来裁判員裁判であるべきものが、平たく言いますと、裁判員裁判面倒だから裁判官裁判にしてしまおうと、そのような運用がされるのではないかということが懸念されましたり、あるいは、裁判所としてもどのくらいであれば著しく長期と言えるのかという基準がないので判断に困るという意見があろうかと思います。
では、この制度を設けるとして、除外事件を設けるとして、その期間や回数を明確に区切ることができるか、又は、そうすることがいいかということであります。
これについては、例えば、あくまで例えばですけれども、百日を超える場合というふうに定めたとして、その場合に百一日との違いはどこにあるのかとか、また、百日超えであっても裁判員が十分に確保できるという見込みがあるのにやらないのかといった疑問が生ずることになるでしょう。
大まかにこれを定めるといっても同じことだろうと思います。期間や回数を区切ってしまいますと柔軟な対応ができないおそれがありますので、個別の判断に委ねることとし、ただし、その事件を担当する裁判官が面倒だからやめようということのないように、別の裁判官の合議体でこれを決することとして、その際には当事者や事件の経過についてよく知っているその事件を担当する裁判所の裁判長の意見を聴くという手続的な障壁を設けて、さらに、決定については即時抗告という不服申立ての制度があるということであります。
また、実際の運用としては、審理計画を立ててみたら、当初から一年、二年掛かるということが分かるようなものであれば選任手続に入らずに除外するということかもしれませんけれども、そうでないものについては、選任手続に入ってみたら困難だということになって、そうした事例がそうあるとは思えませんが、積み重なることで著しく長期、多数の基準ができ上がっていくことが期待されるのだと思います。
したがいまして、基準が明確でないということで恣意的な運用がされるのではないかという懸念がありますけれども、しかし、それに応えるような制度になっていると考えます。
さらに、これまで裁判員の職務従事期間が百三十二日、百十三日といったような事案でも裁判員裁判ができているのだから、除外事件を設ける立法事実がないのではないかという指摘もありそうですけれども、これは、やってみたら裁判員が足りなかったということになったときには既に遅いのでありまして、既に、たしか四日間の審理が予定されていた事件で、ある裁判員がインフルエンザでしたか病気で解任されまして、そのため審理が延期されて、ほかの裁判員も辞退したという事案があったと記憶しております。
法案が想定していますのは元々長い事件ですから、証人の数も証拠の数も多い。既に行われた証拠調べの結果を新たに選任された裁判員に知ってもらう手続を入れて更に裁判を続けますと、その分裁判が延びます。その結果、さきに申しましたように、被告人は裁判制度の都合で待たされることになります。また、裁判員の負担も増大することになるでしょう。これは言わば転ばぬ先のつえでありまして、これまでそのような事案がないということは反対の理由にはならないものと思います。
以上が、第一の点についてでございます。
法案の第二、第三については、特に申し上げることはございません。当然の措置であろうと考えます。
第四は、裁判員選任手続での被害者特定事項の取扱いであります。
裁判では、犯罪の被害に遭った人々に関する様々な情報、プライバシーが明らかにされることがあります。これが流布されることによって被害に遭われた方が被る二次被害は大変なものがありますので、刑事訴訟法には被害者特定事項の秘匿制度、裁判員には守秘義務も課されていますけれども、これは裁判員候補者には現在のところ及んでおりません。
実務的には相当な工夫をして、選任手続で被害者特定事項が伝わらないようにしているとのことではありますけれども、被害に遭われた方にとってはこれは大変な関心事でありまして、念には念を入れて、候補者であっても知り得た被害者特定事項は明らかにしてはならないこととして、ただし、候補者であるという地位に鑑みて、その義務があることのみ法に定め、罰則までは置かないというバランスを取ることを図ったもので、適切な方策であると考えます。
頂戴しました時間に若干余裕がございますので、第一の点について補足させていただいてよろしいでしょうか。
当事者の請求又は職権である事件を除外事件とすると国民が裁判に参加する機会を奪うのではないか、除外事件を決める手続に国民の意見を聞く段階を設けるべきではないかという御意見があろうかと思います。
これについては、まず形式的に、憲法及び法律には裁判員となる国民の権利ないしその機会を保障するという定めはありませんので、裁判員法の立法趣旨は、再三申しますように、国民が裁判に参加する権利を実現するためというものではないと解されます。
そしてまた、より本質的には、裁判員となることがもし権利であるとしますと、これを放棄することもできるはずでありまして、そうすると、国民には裁判員となることを辞退する自由も認められることになるのではないかと思います。しかし、法は辞退事由を限定し、さらに、罰則をもってこれに対処しております。ということは、この制度は国民に裁判員になる権利を保障したものではないと解することになります。
一条が言いますように、国民の参加によって刑事司法への理解と信頼を促進するという政策的な目的を実現するためのものでありますから、したがって、それがかえって国民に負担を課すというものであれば除外事件を設けることができる、このように解されます。
以上です。
○委員長(魚住裕一郎君) ありがとうございました。
次に、小沢参考人にお願いいたします。小沢参考人。
○参考人(小沢樹里君) 本日はよろしくお願いいたします。
私は、関東交通犯罪遺族の会(あいの会)の代表、それから全国犯罪被害者の会(あすの会)の会員の小沢樹里と申します。私は、裁判員裁判について被害者遺族が感じたことと題しまして、ここの場でお話をさせていただきます。
私は、交通犯罪によって義理の両親を亡くした被害者遺族です。義理の双子の弟や妹もこの事件で重傷を負いました。妹は、顔面に複雑骨折し、前歯を十二本も折り、表情が事件前と大きく変わってしまいました。弟は、排尿、排せつ障害になりました。また、妹と弟は共に高次脳機能障害となるなど、七年以上たった今でも大きな後遺障害に苦しんでおります。私は、事件後、夫とともに弟、妹の二人を引き取り、一緒に暮らし、面倒を見ております。
事件の概要ですが、二〇〇八年二月十七日、家族四人が乗った車が埼玉県熊谷市の路上で事件に巻き込まれました。加害者の運転手が飲酒し泥酔状態の末、連続カーブ、時速四十キロの道路を百から百二十キロで走行し、コントロールを失い、反対車線に走っていた二台の車に衝突いたしました。そのうちの一台が私の義理の弟が運転していた車で、妹と両親が同乗しておりました。両親は即死でした。
加害者側の運転手は、既に危険運転致死傷罪により十六年の実刑判決が確定し、服役中です。また、酒を飲ませた飲食店店主も、道交法の酒類提供罪で懲役二年、執行猶予五年、有罪判決を受けました。そして、同乗者二人は、さいたま地裁で危険運転致死傷の幇助罪として裁判員裁判を受け、懲役二年の実刑判決が下りました。
裁判員裁判に関与した内容についてですが、被害者参加人として、夫、弟妹と私の四人が参加いたしました。当初、私、小沢樹里が長男の嫁であり血族ではないので被害者参加ができないとの誤解がありましたが、姻族の直系親族であっても参加ができるという確認が取れ、私も参加人として裁判参加ができました。
証人として、事故当事者の弟妹二人と私の夫、計三人が証言台に立ちました。被害者の意見陳述は、弟妹の二人と私の三人が行いました。犯罪事実については、私が被告人両名に直接質問をいたしました。被害者としての論告求刑も、委託していた弁護士だけではなく、夫が直接行いました。ちなみに、情状事実についても被告人両名に被害者が直接質問しようと思いましたが、後で述べますように、全く納得のいかない形で、訴訟指揮で認められることができませんでした。
裁判員裁判でよかった点をお話しさせていただきます。
私たちは、四人の被告人に対して三つの裁判を経験してきました。危険運転致死傷罪での運転手に対する裁判、道交法の被害者がいないとされた飲食店店主に対する酒類提供罪の裁判、そして同乗者二人に対する危険運転致死傷幇助罪での裁判です。この罪名での裁判員裁判の起訴は全国初でした。
最初の二つの裁判とは異なり、三つ目の裁判だけが被害者参加、そして裁判員裁判が始まって以降の起訴でしたので裁判員裁判となりました。私たちが危険運転致死傷罪の共同正犯で二人を告訴しなければ、道路交通法の同乗罪として裁かれ、裁判員裁判になることはなかったでしょう。また、道交法は被害者なき犯罪として扱われますから、私たちも被害者参加人となることはできなかったことと思います。
この三つ目の裁判員裁判が最初の従来の裁判二つとはっきり違ったのは、裁判が大変に分かりやすかったということです。裁判員に理解ができるように進行したため、突然遺族となった私たちにとっても最初の二つの裁判に比べて十分に理解ができました。
また、私たちは、法律論よりも、事件に関係した人の日常、当日の行動、それが聞きたかったのです。裁判員も私たちと同じ感覚で、普通の疑問を被告人にしていただきました。例えば、同乗者同士であるA被告人と事件当日に一緒に飲んでいたB被告人に対して、裁判員は補充質問で、以前A被告人から暴行を受けたことがあると言っていましたけど、何回ありますかと聞きました。B被告人は一回だけですと答え、裁判員はどういう暴行でしたかと更に聞き、B被告人は拳で背中を何回もたたかれましたと答えたのです。このように、会社内の役職上は横並びであっても、実際の被告人二人には上下関係があったことを的確に裁判員が浮き彫りにしてくれました。
さらに、情状立証に入ろうとしたとき、裁判長は法廷に入ってくると、本日の予定を変更します、裁判員らの強い要望により更に罪体について審理を続けます、ついては証拠請求されていない証拠のうち、B被告人の検察での供述調書を職権で採用したいと考えておりますと宣言したのです。裁判員が強く要望してくれたおかげで、公判前整理手続で検察官が諦めかけた証拠を裁判所によって改めて証拠採用してもらうことができました。これこそが市民感覚の意義と感じました。
また、次にですが、被害者参加制度を利用した裁判員裁判において問題となった又は問題と思われたことについてお話をさせていただきます。
私たちの裁判では、せっかく被害者参加人となって被告人質問をする準備をしていたんですが、情状質問については、被告人が、無罪を主張する以上、情状については包括的黙秘権を行使すると主張したために、裁判所が検察官や私たちの発問自体認めてくれませんでした。私たちが委託した被害者参加弁護士が、黙秘権は黙っている権利であり、相手側の発問自体を制限するものではないと強く裁判所に異議を述べ、少なくとも発問をすることは認めてほしいと求めました。ですが、結局、異議は認められませんでした。私たち被害者は、事件以来ずっと被告人に聞きたいと思っていた情状について質問することさえできませんでした。被告人に聞きたいことがあるから被害者参加制度を利用して法廷に立とうと決めたのに、裁判官の制度への無理解からそれを無視されました。
私たちの疑問を法廷で聞いてもらえなかったことについては、被害者側の問題だけにはとどまりません。私たちの裁判を担当した裁判員にとっても大きな問題となって残ってしまったように思うのです。私たちの疑問が明確にならない状況があったのですから、裁判員にも事実の真相をしっかり理解してもらえなかったんではないかと今でも思っております。
先ほど述べたよかった点と関連しますが、裁判を通して、裁判員が聞きたかったことと私たち遺族が聞きたいことはとても近いように感じました。その一方で、被害者が聞きたいということは法律の専門家が聞きたいこととは視点が違います。事件の真相を追求するとしても、どんな点が知りたかったのか、何を知りたかったのかについては、職業裁判官に比べて、同じ一般市民である被害者と裁判員の方が同じことを考えているように感じました。
職業裁判官だけで判断するのではなく、一般市民の感覚を取り入れることが裁判員裁判をつくった理由だったと思います。被害者遺族と裁判員の疑問や意見が似ているのですから、被害者が刑事裁判への参加制度を利用して、自らの質問を生の声で伝えてしっかり法廷で明らかにすることは、裁判員が市民感覚を生かした判断をするためにも必要不可欠だったと思います。
これも先ほど述べたことと関連いたしますが、私たちの裁判では、公判前整理手続で除外された被告人の供述調書が、被害者の気持ちを理解したと思われる裁判員の強い要望によって、裁判所の職権で復活し、採用をされました。
裁判員の負担を考慮し、審理をスムーズにするための公判整理手続だったはずが、その手続で証拠を絞り過ぎてしまったために裁判所が新たにまた職権採用しなければ裁判員の判断に支障が出るようでは、全く意味がありません。裁判員の負担ばかり考慮する今の裁判所の運用では、被害者の立場からすると、真相を十分に解明できず、不満が強く残ります。
なお、現在、公判前整理手続では被害者が立ち会うことも意見を言うこともできませんが、もしこの手続に被害者側弁護士だけでも参加することができれば、私たち被害者の意向を酌んでもらい、証拠の絞り過ぎに歯止めが掛けられ、結果的に裁判員の理解を助けることになるのではないかと思っております。
証拠については、重傷を負った妹の事故前、事故後の顔写真を証拠採用してもらえませんでした。お手元に資料があると思いますが、見ていただき、御確認していただきたいと思います。裁判員に見てもらうことができませんでしたので、まだ二十代の妹の顔がどんな被害を受けたのか、写真を見れば一目瞭然だったと思います。それを見ていただけたら、事件がいかに悲惨だったということが分かってもらえたのに、証拠採用は強く反対されました。
ここでも裁判員の精神的負担への行き過ぎた配慮のため、過剰に証拠が厳選されてしまったことは強く疑問を感じました。事件を判断する人たちは、証拠から目を背けるのではなく、きちんと事実に向き合って判断をしていただきたいと思います。
最近は、御遺体の写真であれば、何の議論もないまま裁判長が一方的に証拠として採用することを却下していると多くの被害者遺族から聞いております。一見むごい写真でも、むごさに至る前に加害者が犯罪行為をやめようとしなかったという強固な犯意の証拠になるのになどと、遺族の不満はとても高まっているそうです。再審請求しようとしていた死刑囚の妻が、三人の被害者の写真を取り寄せて、見て驚き、もう再審には関わるのはやめて離婚したという話も先日のシンポで伺いました。その奥様は、真実を写真で知ったからこそ考えが変わったのではないかと思います。
犯罪被害者基本法には、被害者にはその尊厳が尊重される権利があるとうたわれており、犯罪被害者等基本計画では、刑事司法は、公の秩序維持とともに、犯罪被害者のためにもあると定められています。裁判員裁判でも、被害者を尊重し、被害者の従来あった姿そのままを見てもらい、本当の被害の現状を知ってもらいたいと思います。
また、裁判員と比べて、被害者の立場で考えさせられたことについてお話しさせていただきます。
私たち被害者は、通常の生活をやりくりして遠方から裁判に参加しているのですが、その横で、裁判員だけが受けられるサービスがあることに私たちは気付きました。保育や介護サービス、決まった回数の心理カウンセリング、電話相談についてです。
裁判員が数日間の裁判に関わることでカウンセリングが必要になるくらい精神的負担が生じる場合があるのも十分分かります。それは、被害者又は遺族にとっても同様です。また、保育や介護については、殺人や交通事犯も含め、常時必要不可欠なことです。介護を担わなければならない遺族が裁判所に通うことができない現状を御存じでしょうか。ですから、被害者も裁判員同様、最低限、保育、介護、カウンセリングを受けられるようにしていただきたいと思います。裁判員への負担を軽減するだけではなく、被害者の負担も軽減をしていただきたいと思います。
最後になりましたが、裁判員裁判で裁かれる事件は、より罪の重いものだと聞いております。それだけに、被害者や遺族には、事件の記憶を呼び起こすことはとても大きな悲しみ、苦しみを伴います。しかし、それでも真実が知りたいのです。だから、裁判に挑むという苦渋の決断をしているということを裁判員の皆様にはまず知っていただきたいです。特に、遺族は、亡くなった家族のために、自分自身を犠牲にしてでも真実を知りたいと思います。
裁判員裁判の制度が今後より多く活用され、被害者の命の重みと人を裁く重みが多くの人に伝わり、社会の多くの人が犯罪を犯してはいけないと思ってもらえるように運用されていくことを切に望んでおります。
ここまで聞いてくださり、誠にありがとうございました。
○委員長(魚住裕一郎君) ありがとうございました。
次に、泉澤参考人にお願いいたします。泉澤参考人。
○参考人(泉澤章君) 弁護士の泉澤と申します。肩書は長いものがたくさん付いておりますが、ただ、今日は一人の刑事弁護人としてここに来て、裁判員裁判に関する話をしたいというふうに思います。
お手元にレジュメを配っておりますが、これに従ってお話をしていきたいと思います。
まず、裁判員裁判、これを導入したときですが、私たち弁護士の間でも様々な意見がありました。今までの硬直化した裁判、官僚的裁判を、国民の司法参加、一般の市民の方々の社会常識を反映させることによって打破するという意味もあるのだろうという意見もございました。ただ、裁判員法一条、これが制定されており、これは司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すると書いておりますが、国民の司法参加への一般市民の社会常識を反映ということは書かれておりません。
当初あった解説によれば、現在の刑事裁判は基本的にきちんと機能しているという評価を前提として、新しい時代にふさわしく、国民にとってより身近な司法を実現するための手段として導入されたとある裁判官の方が解説で書かれております。果たしてそうでしょうか。
その後、刑事司法を取り巻く状況は激変と言ってよかったというふうに思います。偶然かもしれませんが、裁判員裁判が施行された二〇〇九年五月二十一日以降、非常に大きな刑事司法をめぐる状況の変化があったというふうに思います。
一つは足利事件。これは同じ年の五月にDNA鑑定が他人であるということが分かった事件で、私もその弁護団の一員として活動しておりましたが、この足利事件、また布川事件、東電女性社員殺人事件等が再審無罪になるということで、連日マスコミを騒がせたのは御記憶のことだというふうに思います。昨年は死刑事件であります袴田事件、これが、まだ即時抗告審が続いておりますが、再審開始決定が出ております。
このような重大冤罪事件、これまでの刑事裁判において重大な冤罪事件があったのだということが皆さんの目の前に明るみに出たということです。また、厚労省事件、これは最終的には村木さんが無罪になりましたけれども、これをきっかけとして、検察、そして裁判所、さらには刑事司法そのものへの国民の信頼がかなり低下したのではないかというふうに思います。
このような国民の言ってみれば世論を背景にして、検察の在り方検討会議や法制審特別部会、これらが設置されて、新しい刑事司法改革はどうなのだという議論が続けられてきたのだというふうに思います。
このような言ってみれば裁判員裁判施行後の事情を見ると、やはり既存の刑事司法は果たして本当にきちんと機能していたのだろうか、こういう疑問が私はあるというふうに思います。現在の刑事司法が基本的にきちんと機能しているという評価を前提とするという当初の理念は、これはやはり置き換えるべきである。そういう意味では、裁判員法一条、この理念は、やはり一般市民の方々の社会常識が反映される、そのような国民の司法参加、この点に非常に重点を置くべきではないかというふうに私は考えます。
さて、日本国憲法の問題を少し話します。
憲法が刑事手続について詳細な規定を置いているのは皆さんも御存じかと思います。人権規定の中でやはり分量としても一番多いことになっています。憲法三十一条以下、もちろん通常の裁判に関する規定もございますが、四十条まで、これが刑事手続に関する規定になっております。
なぜ憲法上このような刑事手続に関する規定が詳細に規定されているのか。それはやはり、刑事事件、これによって対象とされる人は個人。被疑者、被告人は、国家という大きな権力との間で対峙するという究極の場に置かれるからだというふうに思います。また、そのように習いました。
刑事裁判の手続の原則である推定無罪の原則であるとか、また疑わしきは被告人の利益、このような原則を前提とした刑事手続、その一環として、要するに刑事手続の一環としての裁判員裁判制度、これにも当然ながら生かされるべきであるというふうに私は思います。一人の無辜も罰してはいけない、この考え方が前提となって裁判員裁判制度も運用されるべきであるし、また、改正が必要なのであれば改正されるべきであるというふうに考えます。
その意味で、裁判員裁判の存在意義は、国民の司法参加によって、刑事裁判、この中で特に事実認定がありますけれども、に社会常識を反映させて、最終的には誤判や冤罪を防止すること、そこにこそ重点が置かれるべきではないかなというふうに私、刑事弁護人の立場としては考えます。
事実認定と書いたのは、やはり事実認定、事実のあるなしについては、裁判官はもちろん慣れてはいるでしょうが、プロというふうには言えないと思います。一般市民の方々も、一般の社会の中で生きてきて事実の有無についてはきちんと判断ができる、こういう前提に立っているからこそ、私たちはその国民の常識というものを信頼できるのだというふうに思います。国民の司法参加の持つ非常に積極的な意義、これを重視して私たちは裁判員裁判制度を運用すべきであるし、制度を担っていくべきであるというふうに思います。
最初に述べました裁判員法一条におけるこの理念、これは、現在の刑事裁判が基本的にきちんと機能しているんだと国民に理解してもらう、刑事裁判を理解してもらうというふうなものであれば、国民はやはり客体でしかないわけなのです。教え導かれる客体としての国民でしかないというふうに思います。
しかし、国民の司法参加の持つ積極的意義を考えれば、もはや国民は単なる客体として見ることはできないと思います。民主主義を支える主体としての国民、これが司法の場に参加することこそが積極的な意義を持つのだというふうに思います。それゆえ、国民のこの司法参加を安易に制約するということは、私はできないというふうに考えます。
さて、視点を若干変えまして、私も刑事弁護人ですので、一番気になるのはやはり冤罪です。これらの構造的原因が裁判員裁判とどう関係するかということについて、私の若干意見を述べさせていただきたいというふうに思います。
先ほど様々な冤罪事件が明るみになったというふうな話をしましたが、日本型冤罪事件、その構造の分析というのがされておりまして、様々な原因が言われております。
例えば、長期の被疑者、被告人の身体的拘留、いわゆる人質司法と呼ばれますが、そのようなことや、捜査機関による密室取調べ、そしてそこで得られた自白、これが裁判所では非常に偏重される、そして調書裁判、証拠の偏在、弁護人や被告人の方にはなかなか自らに有利な証拠というものが手に入らない、また弁護人による防御権が弱い、様々なことが言われております。
これらにより今までの重大な冤罪も発生してきたとすれば、それらは裁判員裁判制度が成立することによってどう変容してきたのかということを私は考えるべきだというふうに思います。もちろん、裁判員裁判制度は対象事件が限られておりますから、刑事裁判一般の議論にそのままストレートに入らないかもしれませんが、やはり裁判員裁判制度が今までの、従来の刑事司法に与えた影響というのは、私はあるというふうに思います。
長期の身体的拘束はまだ続いておりますが、しかし、保釈率の上昇ということも言われております。捜査機関による密室の取調べは、これは現在、全面可視化の議論に行っています。まだ遅々として進まないところはあるでしょうが、そのような議論に進んでいる。自白の偏重と調書裁判については、裁判員裁判は公判中心主義によるのだというふうにされ、またそのような運用もかなり進んでおります。証拠の偏在については、証拠の開示、類型証拠開示や争点関連証拠の開示で進んでいるというふうになっています。また、弁護人の防御権についても様々な試行がなされているという、そういうプラス面も私はあるというふうに思います。
個人的体験によると、私も裁判員裁判の否認事件を担当しまして、昨年、千葉地裁で無罪事件を一つ獲得いたしました。それはなぜそうなったかというと、私の分析によると、やはり証拠の開示が非常に全体的なものがなされたということと、それを、裁判長の一つの力量もあったのかもしれませんが、非常に絞り込まずに裁判において出し、また裁判員の方々に適切にそれらを示して説明、指摘を受けたと、そういうところがあったのだというふうに思います。
ただ、マイナス面というものを見逃せませんでした。非常に期間はタイトです、短いです。これはやはり裁判員の方々に負担を掛けないという面はあるかもしれませんが、しかし、ちゃんとした刑事裁判をやるのであれば、ある程度のやはり負担は、私は免れないというふうに思います。この点については、やはり改善する必要があるのじゃないかなというふうに私は考えました。
さて、最後に、裁判員裁判制度改定を含む現在の司法制度改革について、その論議に望むものについて幾つかお話をしたいと思います。
一つは、今まで話してきました国民の司法参加の積極的意義を前進させるために、ここに求められているものを是非議論していただきたいというふうに思います。率直に言えば、国民の司法参加を広げるという意味、前進させるという意味での例えば否認事件の選択権であるとか、そういうことについては議論していただきたいなというふうに私は考えます。
さらに、裁判員制度それだけではなく、それを含めた一体としての刑事司法制度改革の視点としても、先ほど言った、例えば誤判のもとになっておる様々な原因を払拭するような制度改革を更に進めていただきたい。可視化、また証拠開示、特に全面開示を私たち弁護士は求めてきましたが、そういうことについて更に前進させていただきたい。今、ほかのところでは刑事訴訟法等一部改正案も議論になっているようですが、そこではむしろ治安立法であるとか司法取引のような、私から見れば、残念ながら冤罪の可能性を含むような制度が取り上げられようとしていることについては、私自体は危惧を抱いております。
いずれにしましても、国民の司法参加の積極的意義、これを前進させるような議論を是非していただきたい。また、一体としての刑事司法制度改革、これを是非進めて、更に広めて、刑事司法を本当に国民のものとして、誤判、冤罪をなくす社会制度を是非先生方にはつくっていただきたいと切に願う次第であります。
御清聴ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は三人の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
裁判員の参加によって事実認定に社会常識を反映させるという点について、まず小沢参考人からお尋ねをしたいと思うんですけれども、亡くなられた義理の御両親と、そして弟さん、妹さんに心からお見舞いとお悔やみを申し上げたいと思います。
参考人意見の中で、危険運転致死傷幇助罪で同乗者二人が実刑判決を受けた事件に参加をされて、その中での裁判員の補充尋問のお話がありました。A被告人とB被告人の会社内での役職上が横並びであっても、実際は被告人二人の間に上下関係があったことを裁判員の質問によって的確に浮き彫りになったと。その後、職権でB被告人の検察の供述調書が採用されたという、この市民感覚の反映が判決にどのように結び付いたか、生きたかというのは、もちろん裁判員ではなかったわけですからその評議の中身は分からないとは思うんですけれども、被害者御遺族としてどんなふうに感じられたかというのはいかがでしょうか。
○参考人(小沢樹里君) まず、そこについては、やはり危険運転致死傷というのはハンドルを持った加害者ですが、危険運転致死傷幇助罪というのはハンドルを持たない犯罪者なわけです。どこでハンドルを持つだけの幇助をしたのかというのをしっかりと裁判員が理解するとなったときに、その車中の中でどのような会話があったかないかというものを検察側の供述調書の中にはしっかりと書いてあったんですね。それを見たいと、そこに書いてあるんじゃないかというのが裁判の中で争われて、最終的には、そこに関して裁判員の方から見たいということを言われたんです。
実際にはここは争わないという話だったんですが、被告人の方から、そこの部分に関しても私たちはやっていないんだという無罪主張だったので、もう一度そこを見たいということだったのですが、やはり公判前整理手続の段階で証拠が絞られ過ぎてしまったので、そこのそもそも物がないので裁判員が判断をすることができないという状況になってしまって、通常であれば公判前整理手続の中でそれを復活させるということはなかなか難しいんですが、裁判員がやはりどうしてもそこの会話、どういう事実があったかというのをしっかりと見たいという要望があったので、しっかりとそれが裁判官によって職権で採用されたという流れなんですね。
やはりこの段階で、一番最初私が申しましたが、公判前整理手続で私たちは意見を言いたいわけではなくて、しっかりと見極めたいと。意見を言うのは検察官であっていいと思うんですね、やはり公益の利益をしっかりと尊重してくださるのが検察官ですから。そこではなくて、証拠の絞り過ぎ、ここはもうちょっと入れたいんだということを後ででもいいから言えるように、しっかりと公判前整理手続で弁護士でも参加ができるようになれば、この絞り込みがなかったのではないかと考えております。
○仁比聡平君 つまり、今のお話は、職業法曹だけで行われる公判前整理手続で証拠が絞り込まれ、争点は絞られてしまったけれども、実際の公判での審理で裁判員が参加している中で、ここが争点なのではないかということで、裁判員の方の質問を始めとして、争点が復活したというか生きてきたというか、そうしたことなんですか。
○参考人(小沢樹里君) はい、そうです。
○仁比聡平君 逆に、被害者参加をできなかった二つの事件、加害運転手の危険運転致死傷罪事件とそれから飲食店の店主さんの事件、これは極めて分かりにくかったというお話だったんですけれども、職業裁判官が主宰し裁判員が参加をしないこの二つの事件というのは、これどうすれば分かりやすかったと思いますか。
○参考人(小沢樹里君) 何点かあると思いますが、まずは、通常の裁判ですと、誰に理解してもらうという中で、被害者というのは一切入っていないんですね。もちろん法曹者の中の話を聞いていて、加害者自身もやはり話が納得できない状態で、法律用語で話がどんどん進んでしまっているというところが一点。
また、二点目に、傍聴席側に被害者は座っています。通常の以前までの裁判であれば検察官の隣ではなかったので、そうなったときに、やはり声が聞き取りにくいというのもあります。
それから、今は裁判員が見えるようにということで証拠が大きなビジョンで見えるようになっていますが、前回までは、証拠を、ここを示してくださいというので証言台の中で加害者が指したとしても、私たちが見ることができなかったので、裁判の審理の方向性が私たちの方から見ることができませんでした。
また、それから一番大きいのは、やはり証拠を、裁判の始まる前に私たちが実況見分調書を見ることができるというのは非常に大きかったんじゃないかなと思います。何が起きているのかということで、被害者が知りたいのは真実であって偽物のことではないので、そこに関しては裁判員と一緒なのかなと思っています。
○仁比聡平君 ありがとうございます。
今のお話は、つまり、裁判員裁判において、公判中心主義だとか、直接主義、口頭主義だとか、そうしたことが強調される中で感じておられる分かりやすさなのではないかと思うんですけれども、実はそれは刑事訴訟の大原則のはずだと思うんですね。
小木曽参考人にお尋ねしたいと思うんですが、冒頭、裁判員法一条を示されて、参加は国民の権利ではないという立場をまず大前提としてお述べになったんですけれども、そこの、何というんでしょうか、法理的な議論は一応横に置いても、裁判員裁判が施行されて六年たって、実際に職業裁判官だけで行われてきた裁判の中に裁判員が参加するという経験が積み重ねられる中で、今、小沢参考人がおっしゃったような、おのずから事実認定に国民の社会常識が反映していっているというこの現象は当然起こっているし、それは裁判員制度の否定するものではない、裁判員裁判が元々やっぱり内在的に持っているものだと私は思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
○参考人(小木曽綾君) 異論ございません。
ただ、権利として、ある国民が裁判に参加するということを要求するという保障はされていないという趣旨であります。
国民が参加することによって、先ほど私申しましたけれども、裁判が共有財産であれば、それは国民が分かる言葉で語られなければならないし、国民が納得できるものでなければいけないということを申し上げましたけれども、全くそれは今委員がおっしゃったことと反するものではないと思います。
○仁比聡平君 そうした裁判員裁判に、先ほど小沢参考人が、被害者の立場はもちろん、被告人から真相といいますか、を引き出す上でも、そうした覚悟を決めて裁判員の選定手続に臨まれたというお話がありました。
国民の側は、まさかお客さんなんかという位置付けではなくて、自らそうした覚悟を決めて選任に臨んでこられていると思うんです。そうした裁判員裁判から著しく長期を除外するという問題について、結局、小木曽参考人も具体的基準はないとおっしゃっているんだと思うんですよ。手続的には別の裁判体が判断するとかあるいは不服申立てがあるということなんだけれども、著しく長期、多数とは何か、あるいはその判断要素は何かというとその基準はないとおっしゃっているんじゃないかと私は思うんですけれども。
そうすると、例えば一回選任手続を行ったら、先ほどの水戸でしたかの事件のように、水戸地裁のケースのように、審理期間四日間なんだけれども裁判員が出てこないということになったら、そうしたら、これ何だか、裁判員が選定できないから刑事裁判が始められないから、だから裁判官だけでやるのかみたいなことは、これ著しく長期じゃないんだろうとは思うんですけど、どこでどう判断するということになりますか。
○参考人(小木曽綾君) 今おっしゃったように、四日が著しく長期ということにはならないだろうという、これは我々の言葉で言うところの文理解釈でもって、これには当然入らないよねということになるんだろうと思います。
基準が具体的にできないというのは、先ほどから議論がありましたように、はっきり何日というふうに言い切ることは難しいということだったわけです。しかし、誰がどう見ても、四日なり十日なりでこれが著しく長期だよねということにはならないということだろうと思います。
○仁比聡平君 具体的基準がない中で、裁判官の職権で裁判員対象事件から外されてしまうというこの仕組みが一体合理的なのか、裁判員法そのものに本当に沿うのかというのは、私は極めて疑問に思っているんです。
ちょっと別の角度で、刑事裁判としての裁判員制度という観点で泉澤参考人にお尋ねしたいんですが、たしか足利事件の審理の中で菅家さんの自白の供述をした録音テープが法廷で再現された場面があったかと思うんです。その傍聴をしておられた市民の方に伺うと、涙ながらに自白をするその菅家さんの声を聞いて、もしこれが裁判員裁判だったならば裁判員は皆有罪の心証を抱いたのではないかというお話には、本当になるほどと思わされたんですね。
こうした捏造された証拠あるいは自白の強要、そしてその証拠化というものが現に重大刑事裁判において行われてきている以上、裁判員に事実を誤らせないために、証拠開示を含めた適正な刑事手続というのは極めて重要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○参考人(泉澤章君) おっしゃるとおりだというふうに思います。
足利事件の再審公判のときには、菅家さんはそのテープを法廷で流されるのを聞いて具合が悪くなってしまいまして、私、ちょうど隣で付き添っていたんだけれども、途中で退席したりしたこともありました。
なぜかというと、一つにはもちろん嫌な思い出は思い出したくないというのもあるんでしょうけれども、あのテープは検察官の取調べなんですね。実際にはその前に警察での取調べというのがあるわけです。それはテープはありません。そこで彼がどういうことをされて、どういうふうに言ってみれば検察官の前に行っても話すんだよというふうに言われたかというのは、全然出てこないんですね。ないんですよ。その中でいろいろと話も警察の方でされて、彼はそれを信じ切っていて、検察官の前におずおずと出て、やったね、やりましたと。ところが、途中で否認する。そうするとまた優しくなだめられて、また帰ってくると、今度はやっぱりやりましたと泣くというふうなことを繰り返している。
全面可視化した場合にどうかという議論はまたありますけれども、私は、やっぱりその捜査の過程、過程そのものを証拠化しなければ、証拠化という形で残さなければ、やはり菅家さんはどんな裁判制度になっても救えなかったんじゃないかと思います。
あれはDNA鑑定だけの問題で終わっているような感はありますけれども、そんなことはなくて、あれがあったけれども、やはり細かい自白をしているわけですね。なぜそういう自白ができたかということについて分析するのと、やはり教訓としては、捜査過程を可視化するというのは要するに証拠化するということですよね、それが非常に重要である。
証拠化したものを起訴後、弁護人が全面的にそれを見た上で、きちんとした言ってみればその証拠についての評価がなされるようにしなければならないので、あの裁判で私は体験した非常に大きな今でも残っているのは、やはり逮捕から検察に連れていかれてまた裁判までがすごくブラックボックスなわけなんですよね。そこがきちんと証拠化されて、開示されて明らかになり、かつDNA鑑定の問題というものを、科学的にどうなのかということをきちんとやっておれば、私はああいう悲劇は生まれなかったんだというふうに今でも思っています。
なので、先生おっしゃるとおり、証拠、証拠化ですね、それで証拠の開示、特に全面開示というふうに我々弁護人はずっと前から言っていますけれども、それはまだなされておりませんが、その必要性というのは冤罪が起きるたびに非常に言われるわけですね。袴田事件なんかもそうですけれども、何十年もたってから倉庫にあったテープが見付かりましたなんということがもう普通に言われるわけですよ。これはおかしい、これはどう考えてもおかしいというふうに皆さんも思われるわけですね。
なので、やはり証拠の大事さが前提となっているのであれば、それを全面開示しておくというのが、やはり今でもそうですし、これから裁判員裁判制度をきちんと運用するに当たっても非常に重要なことだなというふうに思っています。
○仁比聡平君 ありがとうございました。
時間が参りましたので終わりますけれども、今のようなことがありながら、今度の法改正の議論の中では、特別部会でもここは別の部会に任すみたいな話にどうやらなっているのかなというふうにも思われまして、そういう点も疑問に思っているということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。