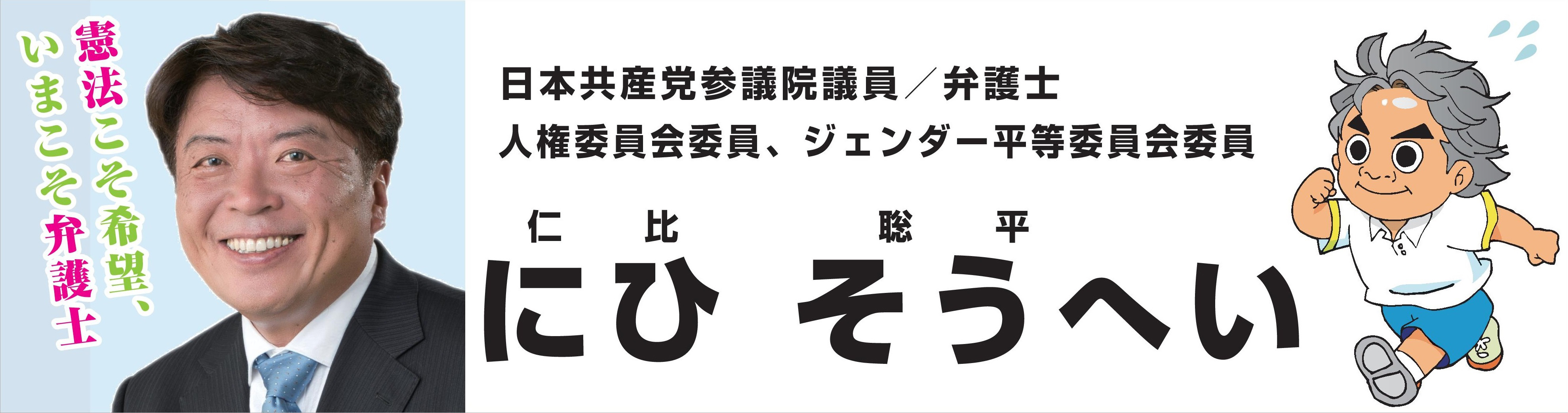○参考人(坂東俊矢君) 京都産業大学で民法と消費者法を教えております坂東と申します。本日はこのような場所で意見を述べさせていただく機会をいただき、心から感謝申し上げます。
さて、成年年齢の十八歳への引下げが議論がされています。なるほど、成年年齢を幾つにすべきかということは、法理論的に定まるものではありません。国民の意識によってその判断をすべき事項であります。ただ、その判断をするについては、民法の未成年者保護法理がどのような意味を持ってきたかということについての共通の理解を言わば国民が持っていることが不可欠であるというふうに私は考えています。したがって、私は、慎重な御検討をお願いしたいという立場でございます。
まず第一に、未成年者に関する規定は、一八九六年の民法の制定時から現在に至るまで同じ形で規定をされています。ただ、こうした規定は、すなわち対等平等な人の例外を規定した近代私法の考え方は、我が国固有のものではもちろんなくて、近代法を有している各国に共通して規定されているものであります。
なぜ未成年者を対等平等な人の例外として保護したのか。その基本的な視座は、市民社会のしっかりとした担い手を育てるために、取消し権の行使をも含めて未成年者の保護が不可欠であると考えられたからであります。
龍谷大学の川角先生は論文で、未成年者保護とは、市民法にとって、担い手を絶えず生み出していくために市民一人一人がその体に刻み込み、尊重すべきところの第一義的な法的価値基準であると述べておられます。私は、そのことをお互いさまの法理だと考えております。この部屋におられる全ての先生も含めて、全ての方が未成年者であったという経験をしています。現在の法律制度の中で保護をされ、大人になってきたわけであります。
どのような市民法としての価値をどうした形で実現をしていくかという課題は、若者に課せられた課題ではありません。既に成人となった大人である私どもに向けられた課題であります。より直截的に言えば、私たちは本当に取引や契約に関する場面で十八歳の若者を大人として迎え入れる覚悟と制度的な準備ができているのかということが問われていると思います。
先ほど先生からもお話がありましたが、高校三年生の生徒さんの中に成年と未成年者が混在することになります。高校三年生でも、親の同意とは関係なく、バイクを買ったりクレジットカードを持つことができるようになります。そうした現実に私たちは対処できるだけの覚悟と準備ができているのかということが問われているのだと思います。
二つ目は、若者の契約に関する消費者被害の救済と被害防止としての意味であります。これは、もう既に多くの参考人も、あるいは国会の場でも大きな議論がされていると思いますので繰り返しをしません。
しかし、さきにも述べたように、民法の未成年者の規定が一八九六年に制定されました。その当時には、消費者問題ということが意識されていませんでした。というのも、契約に関する消費者被害が社会問題になったのは、マルチや訪問販売による契約被害が顕在化した一九七〇年代になってからであります。その画期となった判決として、茨木簡易裁判所の昭和六十年十二月二十日判決があります。
この事件は、いわゆるキャッチセールスで十六万円余りの代金の化粧品等を月一万四千円の十二回払いで購入した十八歳の仕事をしている女性が、親権者の同意がなかったとして取消し権の主張をしたものであります。この事件では、販売業者とクレジット会社は、働くことに親の同意を得ている十八歳の女性であれば、十六万円の化粧品代あるいは月一万四千円の支払は、処分を許された財産の範囲内であるというふうに主張をされました。裁判所はその主張を否定しました。クレジット契約は、御存じのように、一度でも支払が遅れると期限の利益を喪失して全額の支払義務が生じます。したがって、未成年者の処分ができる財産の額をクレジットの分割の金額で判断するのは適切ではないというふうに判断したからであります。そして、この女性が月々七ないし八万円の手取りを得ていたという事実を認定して、十六万円余りの化粧品という金額は、処分を許された財産としては高額に過ぎると裁判所は判決をしました。
実はこの当時、クレジットカードは、十八以上の未成年者であっても、親の同意なく作ることができるという現実がありました。その結果、十八歳を超える未成年者に対して高額な商品が分割払の形式で売られ、消費生活センターの現場でも、それを未成年者取消し権、親の同意がないということを理由として未成年者取消し権で取り消すことが可能なのかどうかという点について迷いがありました。この判決は、こうした現状に対する警鐘となり、結果的に、未成年者取消し権を典型とする民法の未成年者法理に、消費者保護としての意義、機能があることを明らかにすることになりました。
こうした経緯、つまり、時に取引の現場は、未成年者保護法理との緊張関係を生じさせるような現実を生み出してしまうということがこの判決の在り方からは御理解をいただけるのではないかなと思います。成年年齢を十八歳に引下げを考慮する際に、こうした取引の現実をどのように評価するかということについて、私たちはきちんとした整理が必要なのだと思います。
三つ目に、いや、実は、未成年者の民法の法理の中には未成年者が徐々に大人になっていくについての段階的な準備が組み込まれていて、それが実はかなり有効に機能しているということをお話ししたいと思います。
釈迦に説法で恐縮ですが、民法は、未成年者であっても、法定代理人、多くの場合は親ですが、親の同意を得なくても契約ができる場合を定めています。その中でも、第五条三項の、法定代理人によって事前に処分を許された財産に関する規定がとても重要だと思います。
私は、講義で学生たちに、この例として、小遣いとか仕送りとかは、個々の契約をするについて親の個別の同意を得なくても契約をすることができると説明をします。考えてみたら当たり前で、私の大学にも、一回生、二回生、十八歳、十九歳の学生たちがいますが、コンビニで弁当買ったりお茶を買ったりするときに、携帯電話を取り出して、お父さん、今から同意してくれるなんという姿を見たことはありません。それはなぜか。そういった契約は、未成年者であっても小遣いの範囲内で自由にできると民法が決めているからです。
まず、未成年者の年齢というのは、出生から二十歳まで、非常に幅が広いものです。
生まれた赤ちゃんから恐らく六歳ぐらいまでは民法上の意思能力が認められませんから、単独で契約をすることというのは考えられません。しかし、小学校になれば、小学生になれば、親からお小遣いをもらいます。そのお小遣いで、例えばおやつを買ったり、小学校の高学年になったら恐らく文房具を買ったり、そういった契約を自分でするようになると思います。中学生しかりです。高校になったら、日常で自分が着るTシャツやそういったものぐらいは、洋服ぐらいは恐らく親の同意なく契約の締結をしているはずだと思います。そして、そのことを民法は認めているんです。
高校を卒業する十八歳という年齢は、とても画期となる年齢です。先ほど先生のお話にもありました。働く方もいるでしょう、大学に進学する方もいるでしょう。働くためには雇用契約という契約を締結しなければなりません。学生になって京都に来るときには、多くの学生が京都に来てくれますが、下宿をしなきゃいけません。賃貸借契約という契約を締結するわけです。先ほどまでお話をした、高校生として契約を締結するという経験と、十八歳になって働いたり、あるいは下宿をしたり、そういったことで経験する契約は質的に大きく違います。大学に入学が決まった学生たちが親とともに京都にやってきて下宿を探し、親とともに契約を締結します。そのことは、私から見て自然なことです。
その学生たちが二年間大学で学びます。学生課でいろんな話を聞くでしょうね。先輩の下宿に行って相場観を知るかもしれません。いや、就活のためには京都のどの辺りに住んでいた方がいいよねという話を自分で判断できるようになります。言わば、十八歳から二十歳までの間に、大人になる、徐々に大人になっていくというステップが組み込まれているんです。最終のレッスンの時間として、この二年間、学生たちは大きく成長すると思います。
未成年者は、なるほど、例えば、借金をしたり高額な商品や投資的取引を契約したりすることについての自己決定権は制限されています。でも、少なくとも、その学生たちが、日常的な取引についての権限は、その年齢に対応して、その意味を学びながら締結できることになっています。言わば、民法の仕組みの中に、自己決定を練習して積み重ねながらゆっくりと大人になっていくことが準備されているのです。そして、その仕組みは、私はとても有効に機能していると考えています。
もちろん、私は、成年年齢をどうするかという問題は国民の判断だと一番最初に申し上げました。十八歳にするということ自体を否定しているわけではありません。しかし、そのためには、今ある民法の規定の適切な評価をした上で、それに関する国民の意識がきちんと整理された段階で物事の準備を進めるべきであるというふうに考えています。
小児科医で、九州大学の先生をしている佐藤先生という人が、「大学で大人気の先生が語る「失敗」「挑戦」「成長」の自立学」という若い世代に向けた本を書いておられます。その先生が、大人として自立するためにはまず自らが努力しなければならないとした上で、そのためにはすてきな大人を探しなさいと提案をされています。そして、大学生になると、尊敬する人はという質問に対する答えが一挙に広がるというふうにも書いておられます。
未成年者に対する保護法理は、その理論的な意味からも、その法理に組み込まれた徐々に大人になる仕組みという具体化の観点からも適切に機能しています。そして、それは、社会と国民に受け入れられています。成年年齢の改定に当たっては、こうした点に対する慎重な御検討を心からお願いしたいというふうに思います。
良識の府としての参議院での丁寧な御議論を期待して、私の発言を終わります。
ありがとうございました。
○委員長(石川博崇君) ありがとうございました。
次に、遠山参考人にお願いをいたします。遠山参考人。
○参考人(遠山信一郎君) おはようございます。
お手元にある私が作りました参考人陳述骨子に従って陳述させていただきます。
まず、済みませんが、図一、負のスパイラルという図解をちょっと見ていただきたいと思います。
成年年齢引下げによる子供に対する悪影響というものについて、マイナス、負のスパイラルがあるんじゃないかということで図解をしてみました。真ん中の下辺りから、離婚後の一人親家庭の困窮化というところから、児童虐待の要因、それから子供の教育機会の喪失、ワーキングプア化というふうな記述がありますが、これは我が国の深刻な現実だというふうに私は考えています。
この離婚後の一人親家庭の困窮化に対して、図でいうと上の方から、成年年齢の引下げ、離婚後の養育費の支払終期の繰上げ、それから養育費支払総額の減少という形での影響がマイナスに働くのではないかと考えております。この養育費支払総額の減少については、現実というよりは、現実性が極めて高い危機的な状況であるというふうに私は認識しております。
今、政府の方は、一人親家庭の支援については、子育て・生活支援策、それから就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策の四本柱を提示しています。ということは、養育費自体が国策、政府の政策の中の柱の一つになっているという状況なのですが、離婚の際の養育費については、取り決めていない、取り決めても低額、取り決めても支払わないという課題が、実に私が若い頃から、つまり新人の弁護士さんの頃から未解決で、そして山積み状態にあります。ということは、成人年齢の引下げは、そのまま今の脆弱な養育費が更に少なくなることが危惧されるということでございます。
済みません、お手元にある図二を見てください。
この養育費の支払義務の終期については、理屈が結構ややこしい話になります。つまり、成年年齢という形式と成熟年齢という実質が別物なのですが、これは理屈上そうなっているんですが、残念ながら、国民の意識というか実務は、どうしてもこの終期を形式的な年齢の方に傾きます。理由を述べると長くなりますので述べませんが、現実の主流は、今二十歳が主流だと思います。これが、成年年齢が十八になれば、まず、ほぼ間違いなく終期は十八の方に収れんするだろうということは予想されます。
ということで、こんなリスクをどうやって回避したらいいんだろうということを私なりに、これは、どっちかというと弁護士というよりも経験値から考えているのは、まず、家庭の守護神を期待されている家庭裁判所の組織の拡充、機能の拡大。ちょっと抽象的に言いました。できれば、養育費の算定ルール、基準をかなりアップ・ツー・デートに世間に公表するなりしてルールを作ってほしい、実務ルールを作ってほしいというふうに考えています。その背後にあるのは、法は家庭に入らずという時代から、家庭にも法の支配をという時代へ多分転換しているんだろうというふうに考えている次第です。
さらに、養育費の確保のための制度アイデア、制度の拡充をみんなで考えていこうということが大事だと思っています。一例を、済みません、思い付きで挙げたのですが、国の方で最低金額を決めて、それを履行を強制しちゃえ、しまおうというような制度設計もありかなというふうに思っている次第です。
さらに、資料を、ちょっと済みません、見ていただきたいのですが、読売新聞の記事が参考資料の三というところに付けさせていただきました。
これは、私の問題意識を要するにジャーナリズムの方が引き受けてくれて発表していただいた記事なのですが、ここでは、やはり、大学を目指す人、それから大学生という方々が、実に養育費との影響力が事例として紹介されています。ここにも書いてあるとおり、親に道を閉ざされたくないという表題にあるということが、ここにあるその物語、エピソードは、レアケースではなくてワン・オブ・ゼムというふうに考えてよろしいんじゃないかなというふうに思っていまして、こういった立場にある、勉学によって自分の未来を切り開こうという人たちの支援について、親に道を閉ざされちゃったのであれば、国が道を開いてあげようというふうに考えてあげるのがよろしいのかなというふうに思っています。
その意味では、子供は親を選ぶことができませんので、どんな環境に生まれたとしても十分な教育を受ける権利はひとしく保障されるように、優しい気持ちで政策をつくっていただけたらというふうに思っております。
ちょっと話を変わって申し訳ないのですが、図三を見ていただきたいのですが、これちょっと説明させていただきますと、我が国の人口構造は、かつてピラミッド構造から、今どきはひつぎ型というふうに言われています。このまま行くと逆ピラミッドになってしまうかもしれません。
そうしますと、未成年者時代、成年者時代、高齢者時代というふうにざっくり分けたときに、今この引下げというのは未成年者時代を短くする。私のような高齢者については六十出発で、高齢者は七十にしちゃうとか八十にしてしまうということになると、このひつぎの中に入っている引下げ、引上げの矢印を広げることによって、形式的には社会の担い手、ちょっときれい事を言いますと、市民社会のフルメンバーシップ層、自立、自律した家庭人、消費者、労働者、事業者層を拡大するということになると思います。これ自体はもうこの国の今の状況からすると仕方がないのかなと実は思っておるんですが、問題は、形式的にこの社会の体幹というべき市民社会のフルメンバーシップ層を広げたときに、さらに、その実質、社会の体幹を力強く健常化するというか頑健化するために、未成年者、特に未成年の未成熟者に十分な自立力を付けさせるための支援策がとても重要だなというふうに思っている次第です。
とりわけ、今日の私のテーマでいいますと、繰り返しになりますけれども、勉学によって自分の未来を切り開こうとしている若年層の人たちに教育の機会を保障するような政策を、多様なエビデンスに基づく政策立案をしていただくということを期待したいと思います。
以上です。
○委員長(石川博崇君) ありがとうございました。
次に、竹下参考人にお願いいたします。竹下参考人。
○参考人(竹下博將君) 私は、実務家として事件に携わりながらも、養育費の算定ということに関しまして十年以上研究をしてきました。平成二十八年の十一月には、日本弁護士連合会の方で養育費について新算定表というものを提言しましたが、その作成にも関与しております。これまでに全国の半数以上の弁護士会で養育費の算定に関する研修をしてきましたし、先月には、養育費相談支援センター、こちらは厚生労働省の委託事業ですけれども、そちらでも研修の講師を務めています。
私は、本日、こういった立場から、養育費の算定に関わってきた立場として、成年年齢の引下げが養育費に関してどのような影響を与えるのかということをお話ししたいというふうに思います。
先に結論の方から申し上げますと、成年年齢の引下げというのは、養育費支払期間の終期については、これはもう繰り上げるということになると思いますし、それから、大学の費用というところに関して言うと、これはもう分担されなくなっていくであろうと、養育費としてはですね、そういった事態になるというふうに思いますので、成年年齢の引下げについては慎重に考えていく必要があるのではないかというふうに思っています。
引下げをするというのであれば、大学への進学とかそういったことについてどのように経済的に支援をするのかという、そういった制度の整備というところをよく考えていく必要があるのではないかなというふうに思います。
今から具体的にお話をしていくんですが、成年年齢の引下げによって養育費について受ける影響というものをお話しする前に、まず現状をお話ししたいというふうに思います。
現状は、二点お話ししたいと思うんですが、お手元には私の方から資料を二つ用意させていただきました。番号を振っていなくて申し訳ないんですが、六ページの方から始まる資料というのは、こちらの方は元裁判官が養育費の現状について最近記されたものです。それから、百十二ページから始まる方の資料は、こちらは弁護士が最近養育費の現状について記したものです。ですので、弁護士が記した資料と元裁判官が記した養育費の現状についての資料を見ながらちょっとお話をしたいと思うんですが。
まず一点目、現状についてですけれども、養育費の支払を受ける対象となる子供の範囲についてお話ししたいと思います。
遠山さんの方からもお話があったと思うんですけれども、養育費の支払の対象となる子供というのは、これは未成熟子と言われていまして、未成年者ではないと。未成熟子と未成年者の、これは実質と形式というお話がありましたので、これはそのように考えていただいていいのかなというふうに思うんですけれども、実際に養育費の対象となるのは未成熟子というふうには一応考えられていると。
ここで、その元裁判官の方の資料の七ページの方には裁判例が紹介されているんですけれども、その裁判例を見てみると、これは、成年に達しているという子供であっても、自分で生活していくだけの能力がなければ、それは、成年に達しているというそれだけでは、未成熟子ではと考えるべきではないのかという点をよく考えましょうと、そういうような判断をしている、そういう裁判例になります。
そうすると、こういった裁判例というのを見てみると、裁判所は、積極的に未成熟子であるかどうかを判断しているのかなというふうに思われるかもしれませんが、実際はそうではないというふうに思います。実務感覚としては違うというふうに思っているんですが。
弁護士の方の資料、こちら、百十二ページの方なんですが、この百十二ページの下の方に書かれているかと思うんですけれども、実務では、未成年の子を一応未成熟子として扱うというふうになっているんですね。これをもう少し説明しますと、未成年者であるということになれば、実際に働いているといったそういう事情がない限りはもう未成熟子として取り扱おうということになりますし、逆に、もう成年に達しているということになりますと、これは、養育費の支払を受けなければならない特別な事情がない限りはこれはもう対象ではないんだと、養育費の支払を受ける対象ではないんだというふうに取り扱われると、そういう意味になるかと思います。
今年に入って、ある裁判官が次のように話していました。大学に行っているというだけでは、成年に達した子供について未成熟子として判断することはできないと。つまり、大学に行っているだけでは、それだけでは養育費を支払うかどうかは分からないので、もう少し実質を検討する必要があると、そういうように裁判官は最近述べているんですね。これがかなり実務感覚に近いところじゃないかなというふうに私は思います。
こういう考え方を背景にしているのだと思いますけれども、実際実務においては、特別な事情がない限り、養育費の終期は二十歳、二十歳に達する日の属する月までというふうにされていますし、裁判所の方で用意されている書式でも、基本的に、未成熟子というような記載ではなく、養育費については未成年者というような記載がされているところです。
話がちょっと長くなってしまいましたけれども、二点目には、現状としてお話ししたい二点目ですが、大学に進学した後の学費の取扱いがどうなっているかという点です。
この点については、こちら、裁判官の方の資料を、六ページの方からの資料を見ていただきたいんですが、これの百三十四ページというところに大学進学後の学費の分担に関する裁判例が紹介されています、百三十四ページですが。
こちらの裁判では、非監護親の方がその大学への進学について同意していたかどうか、あるいは大学への進学自体について同意していたかどうかと、そういったことが問われているんですね。つまり、大学に進学するということについて非監護親の同意、承諾があるのであれば、それは同意があるので養育費として学費についても分担しましょうということになるわけです。他方で、非監護親が進学について同意、承諾していない場合はどうなるかといいますと、実務上は、親の経歴であるとか親の収入であるとか、進路について親がどれほど関心を持っていたであるとか、あるいはほかの兄弟姉妹はどうだったかと、そういったようなことを総合的に考慮しまして、その上で大学に子供が進学するということがこれは相当であると考えられるのであれば、その場合には学費について非監護親も養育費として分担しましょうと、そういうように考えられています。
こういったように、実質を判断しようという背景には、未成年者の五割は大学に進学していますし、専門学校等も入れれば八割が、高等学校卒業者の八割は進学しているということが背景にあるんだと思います。
ただ、今申し上げたように、総合的に考慮するというような形で判断しますと、どういった場合に大学の学費が分担されるのかは正直よく分からないんですね。そうすると、基準としてはなかなか明確であるとは言い難いですし、また、これも実務の感覚として、大学の学費というものを、非監護親が同意していないのにこれを分担してもらえるといったようなことはなかなかこれは難しいなと、ハードルが高いなと正直感じているところです。
こういったところの背景としては、養育費を裁判所が決めるということは、これは権利義務があるとかないとかいう判断を裁判所がするのではなくて、裁判所としては、公権的な立場で裁量的に負担をさせようと、義務を課そうというものですので、そうすると、そういった金銭的な債務を裁判所が積極的に課すというような場合には、かなり慎重に判断をするというところも背景にあるのかなというふうに思っています。
結論としては、進学について非監護親の同意がない場合は、学費について養育費として分担されるかどうかは予測がし難いということになると思います。
弁護士の方の資料の百二十七ページにはあるんですが、このような指摘がされています。百二十七ページでは、子供の立場に立てば、経済的な問題のため進学できないかもしれない、そういった不安にさいなまれながら困難な受験勉強を乗り越えるというのはこれは容易ではないと、こういう指摘がされていまして、それは私もそのように思うところです。
次に、では、成年年齢の引下げが養育費にどのように影響を与えるのかということをちょっとお話ししたいと思いますが、これも、今のお話しした現状を踏まえて二点お話ししたいと思います。
まず、養育費の終期、支払期間の終期についてお話ししたいと思いますが、法制審議会の最終報告書では、繰り上げるといった意見もあるといったようなお話がされていたかと思うんですが、日本弁護士連合会の方では、平成二十八年二月の意見書で、事実上、そのような成年年齢の引下げによって養育費の支払終期というものが繰上げに直結するのではないかと、そういう疑念が拭い去れないというような指摘がされていると思うんですが、さきにお話ししましたとおり、実務においては、特別の事情がない限りは、成年に達した子供については養育費の支払を受ける対象にならないと考えているわけですので、今般成年年齢が下がると、引き下げられるということになれば、これは養育費の終期も原則十八歳になるというふうに考えることが自然だと思います。
実際、成年年齢の引下げというのはもう見込まれる状況にあるというわけですので、養育費の終期を十八歳にしましょうという調停委員、裁判官はもう現れています。この点については、調査室の方から私いただきました資料の新聞記事でもそういった、これは平成三十年五月二十六日の朝日新聞ですけれども、そのような弁護士のコメントがありまして、これは私が実際に感じているところと同じだなというふうに思いました。
したがいまして、成年年齢が引き下げられれば養育費の終期が早まること、これはもう避け難いというふうに思います。
どのような問題があるのかというところで、この審議の中では、既に合意された場合に、養育費の終期を成年と書いていた場合に、これが成年年齢の引下げに伴って十八歳になってしまわないかといったような質問等があったかと思うんですけれども、この点、私余り心配していませんで、というのは、当時の意思を合理的に解釈すれば、それは二十歳だろうと思われると思いますので、その点は余り心配していませんし、もしもその合意が調停やあるいは審判という形であったならば、強制力があるわけですので、単純な思い込みで十八歳だというのはなかなかしんどいかなというふうに思うんです。
そうではなくて、私が心配するのは、成年年齢が引き下げられるということになりましたら、そのような法改正を理由として、事情に変更があったと考えて、成年年齢の引下げに伴って養育費の終期を十八歳にしてくれと、そういった非監護親が出てくるのではないかなというふうに思うのです。あるいは、ある程度期間がたって、十八歳というのが大人だということはもう常識になったではないかと、だから、法改正からも時間もたっているし、社会常識にもなったし、やはりこれは十八歳に引き下げてくれと、そういう話になってくるのではないかなと。
養育費というのは未成熟子という話でしたけれども、未就学児、例えば五歳とか四歳で取り決めた後もずっとその金額払われるということが往々にしてありますので、五年、十年たって、やっぱりもう今だったらこれは十八にしてほしいんだというようなことを申し出て、裁判所に言ってくる方も出てくるのではないかなと、そちらの方を私は危惧しています。
もちろん、収入の増減とか、いろいろとそういった事情に変更があれば、養育費についていろいろと変更してほしいというお話はあるわけですので、今申し上げたように十八歳に繰り上げてほしいというのもあれば、逆に二十二歳に繰り下げてほしいということもあったりするわけですけれども、なかなか、実は養育費を決めるというのは、まあ離婚に伴うことが多いと思いますけれども、離婚は人生のイベントとしてはかなりエネルギーを使うイベントでして、あのエネルギーをもう一度使ってやろうという気になる方はなかなかいらっしゃらない。そうしますと、私の依頼者でも、養育費をまた上げてほしいんだというような、大学に進学するので上げてほしいといった相談があっても、実際にそれを調停や審判まで運ぶという方は実際には少ないなと、そう思っていますので、先ほどもお話ししましたけれども、幼年期に五歳とか四歳とか決めた金額がずっと行くというのが実は養育費であったりするのかなと、ちょっと話が横にそれてしまいましたけれども、思っています。
いずれにしても、そういった状況ですと、成年年齢引下げ後には、いずれ裁判所の方も、そういった事情変更があったから、養育費の終期については二十歳と決めたけれども十八歳に繰り上げましょうという裁判例が出てきてもおかしくはないのではないかなと私は思っています。
法務大臣の答弁では、そのような懸念についてはいろいろと周知を図ると、成年年齢の引下げというものが養育費の支払期間の終期を早めるものではないといったような答弁があったと思うんですけれども、なかなか実務は、そのようなことは明文がないと難しいなと思われますので、そういったことを何らかの形として残しておく必要があるのではないかなというふうに思っています。
二点目に、与える影響の二点目ですけれども、大学の学費のお話をしたいと思います。
こちらは、先ほどお話ししたとおり、同意があれば、それはもちろん、非監護親が同意していれば大学の学費についても分担されるわけですから、その点は成年年齢の引下げというのは特に影響ないかなと思うんですけれども、そうではなくて、非監護親の方は同意がないという場合は、これは特に夫婦間の葛藤が高い場合にはなかなかそういう連絡を取って同意してもらうということは難しいと思いますけれども、そうすると、実際には同意が得られないので、じゃ、大学の学費についてはどう分担してもらうかというと、それはもう親の経歴とか収入とかいろんなことを総合考慮して、これは分担してもらおうということになるわけですけれども。
ただ、そうはいっても、成年年齢が引き下げられれば、大学生で未成年者というカテゴリーが消えてしまうわけですね。そうすると、そもそも大学に行くというのは、これは成年になった者が行くところなんだと、そして、おとといだったかと思いますけれども、参考人の回答の中にも、大学に行くというのは、本来的には自立するんだったら、それはもう経済的にも自立して自分のお金で行くんだというようなお話があったかと思うんですけれども、そういったような社会意識というものが醸成されていきますと、結局、裁判所としても、学費というのはそれは自分で稼ぐのだというような意識になっていくわけで、そうすると、総合考慮して学費の分担をさせるといっても、かなりそれはケースとしては限定されていくのではないかなというふうに思います。
したがって、支払終期が早まるだけではなくて、大学の学費を分担するということも、これも養育費としてはなかなか難しくなってくるんだろうなというふうに思っているところです。
したがって、大学に進学するということについては、自らの力で何とかしてお金を調達するなり、あるいは監護親、つまり一人親の場合の親の方ですけれども、実際の監護をしている親がそれなりに裕福であるといった、何らかのそういう経済的な状況がないと難しいだろうと。実際、働きながら大学に通うということもできないわけではないと思いますけれども、それで学業に集中できるとはとても思えません。実際、破綻して破産の相談を受けたことは一件、二件ではありません。
そうすると、こういったことに対してどのように対処していくのかということが、成年年齢の引下げに伴って、特に養育費との関係で立法政策として期待されるところではないかなというふうに私は思っているところです。
私の話は以上となります。御清聴ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、四人の先生方、どうも本当にありがとうございます。
まず、坂東参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、今日も様々な角度から問題が掘り下げられているわけですが、参考人の御専門である消費者法の分野、あるいは遠山、竹下両参考人から厳しく出ています親の監護義務や子の養育費などに関わって、ちょっと端的に要約してしまえば、大学生で成年と、大学生は皆成年と、これは学費は自己責任と、そういう社会になっていくのではないか。その下で、十八歳で独立したんだということで、自ら交渉力を持って、典型的にはこれ、親の関係が破綻している場合ですね、その非監護親に対する交渉を自ら行い、その責任は自分で負わざるを得ないと。そうした社会モデルといいますか、ということがシビアな形で示されてもいるのかなとも思うんですが。
坂東参考人が、自己決定を通して徐々に大人になる仕組みとしての未成年者保護法理、こうしたものとして現行民法の考え方を示しておられること、とても私は胸に落ちるものがあるんですけれども、そのお立場から、今日話題になっている諸問題についてどのようなお考えか。この成年年齢が十八歳に引き下げられるとすればどんなリスク、危険があると考えるかはいかがでしょうか。
○参考人(坂東俊矢君) 大学生になった途端に、例えば経済的なところやあるいは契約に関わるものも全て自己決定の範囲内に任せていいのか、あるいは、自分の将来に関わる教育に関わる費用は基本的には自分で支弁するのが当然であるといったような社会で本当にいいのかというところについては、私はとても大きな疑問があります。
やっぱり先ほどの、何といいましょうか、養育費の先生方から御指摘のあった問題も、言わば大学で勉強することについてどういう援助を、仮に別れたとしてもです、親がしていくのかというところが現場では問われ続けているわけですよね。だとすると、そこに関する手当てというのは、社会が健全に発展していくためには必要な話なんだと思います。
いずれにしても、ある段階で、階段上るみたいに、ここからは大人だよねということを言わざるを得ないのは事実だと思います。しかし、それは、それまでの社会的経験や現実のいろんな問題に直面したことのない高校生から大学生になる瞬間にそれを求めるのは、やはり無理があると思います。
したがって、徐々に大人になると言いましたが、とりわけ私は大学生になってから、先生は二十歳まだあれだとおっしゃったけれども、二十歳になるまでの二年間に、実際の様々な契約を一人で経験するという場面で様々なことを現実には学んでいるという経緯があって、その部分の価値を小さく見てはいけないのではないかと思います。
○仁比聡平君 ありがとうございます。
もう一問、坂東参考人に、今のお話しいただいている、その徐々に大人になる仕組みというものを、講学上といいますか、法律学の考え方でいうと、以前は行為無能力制度というふうに呼び習わしておって、戦前は、妻とそれから子、未成年者はこれは無能力者だという考え方だったわけですね。民法の条文そのものは以来変わってはおらないんですけれども、坂東先生にお示しいただいている、この徐々に大人になる仕組みと、そして、その大人になる仕組みの言わば援助者というんでしょうか補助者というんでしょうか、その親権者を法定代理人としている、ここの、親権者に係らしめているというここを、今、先生や、それから先ほど内田先生のお名前も出ましたけれども、現在の民法学会の中ではどんな考え方になっているのかという点についてお話しいただけますか。
○参考人(坂東俊矢君) まず一つあるのは、先生も十分御存じのとおり、現在、制限行為能力者制度という制度になっていて、そこには未成年者も含めて四類型あるということですね。ただ、被後見人とか被保佐人とか被補助人は家庭裁判所の審判を必要としています。それまでフルの能力を持っていた方を、言わば家庭裁判所の審判で限定するという仕組みです。
ところが、未成年者という概念は、先ほど申し上げたように全ての人が経験する言わばものです。そこはかなり違っていて、フルだった方を家庭裁判所で制限するという仕組みと、それと、今からフルにしていくためにどういうふうに法律は関与するか、同じ制限行為者の中でもそこで求められている形は相当違うんだろうなと、まず私は思います。それが一点です。
それから、二点目の御質問では、要するに、親権者の関与ということだけで民法の今考えている未成年者の自立に向けたものが十分かどうかということにつながっている御質問だと思いますが、現在、もちろんこういった議論がなされるようになって、例えば、現の国民生活センターの理事長をされている松本恒雄先生であるとか、あるいは東京大学の大村先生であるとか、いわゆる代表的な民法の先生方が、その部分について客観的に評価できる方法はないだろうか。
つまり、親の同意ということになるとなかなか外から見て見えにくいし、例えば、先ほどの話でいえば、親は小遣い使っていいよと言ったんですが、私などは、仮に小遣い五万円もらっていたとします、そんなもらえないかもしれませんが、五万円で高い毛皮のコートを買うなんていうことは親がそもそも想定していない。小遣いとしての使い道の枠というのがきっとそこにあるんだと思うんですが、その基準というのはある意味では曖昧です。曖昧ですので、できたらもう少し分かりやすい規定がないだろうか。加えて、従来の無能力者から制限行為能力者という流れの中で、そこでは後見人としての親の関与をもう少し小さくしてもいいんではないだろうかという話は、民法の先生方の中でも議論がなされていると思います。
とりわけ、成年被後見人ですらという言い方がいいかどうかは別にして、日常生活に関わる契約は後見人の同意を得なくてもできるわけです。だとすると、そこで導入されたアイデアを未成年者のところにまで何とか使う道はないだろうかというところでいくと、多くの先生方が類推適用していいんじゃないというところまでは学会レベルでは来ていますが、先ほど、実務の現実まで行くと、それはまだまだ議論の途上の話だと思います。
ですので、この点に関する民法改正などについてもやはりある段階で議論し、並行して成年年齢の引下げできると本来であればいいのになという思いが少しします。
○仁比聡平君 ありがとうございます。
遠山参考人、竹下参考人にお尋ねしたいと思うんですが。まず、遠山先生、法務大臣が、この国会での答弁で、十八歳という年齢について、大人の入口に立ったと言えるだけの成熟度という答弁をしているんです。大人の入口に立ったというその意味がどういう意味ですかというのが一つの議論にもちろんなるわけですが、これは、養育費の概念でいう未成熟子か、それともそうではない成熟した人かということでいうと、まだ成熟はしていないということなんだと思うんですが、未成熟子という概念はそもそもどういう人のことをいうのか、どういう子のことを未成熟子というのか。
それから、十八歳に成年年齢が引き下げられれば、十八歳になった後も、例えば大学卒業までという、二十二歳という、ここまでが未成熟と見るべきではないのかという議論があるんじゃないかと思うんですが、この十八歳からその未成熟子である間の子に対する養育費の支払の法的な根拠、これ、竹下先生からは、先ほど、生活保持義務であるものが扶助義務に変わってしまうのではないかという趣旨の御発言もありましたが、遠山先生はどのようにお考えでしょう。
○参考人(遠山信一郎君) まず、ここら辺の問題は、ベースは扶養ということになると思います。扶養というのは、例えば親子関係、夫婦関係で内容が違ってくるものですが、基本的に家族の共同体の中で扶養し合うというのがベースにあって、それが親子とかそれから夫婦とかという関係性の中で内容が変わっていくものなのかというふうに考えていまして、私の、済みません、参考人陳述書骨子の図二のところに、当時、先生と同じようなことをいろいろ思いを巡らせたときに作った表なんですね、これが、図、養育費支払義務の終期というところなんですが。そこで、未成年って何といったら、年齢を基準とした形式的概念。それから、未成熟って何といったら、自活不能を基準とした実質的概念。だから、自活することが実質的に不能だよねという人が未成熟な人。未成年というのは、ありていに言えば、法律で決めたラインで決まるだけのことというふうに考えています。
だから、十八が未成熟なの、成熟なのというのは、答えとしては、成熟な人もいれば未成熟な人もいるという言い方しか絶対できないと思います。それを、十八を、言わば、ほぼ等号とは言いませんが、イコールとは言いませんが、成熟というふうに判断することは、これはむしろ、怒られちゃうかもしれないけど、ナンセンスだと思いますけど。
○仁比聡平君 竹下先生にも同じ問いと、あわせて、先ほど来、平成十五年の算定表のアップ・ツー・デートとか、あるいは、遠山参考人からは、交通事故の場合の赤本、青本に匹敵するような基準化といいますか、そうした御提案もあったんですけれども、その実現可能性ですね、現実の家庭裁判所の今の組織体制だったり、それからあるいは調停あるいは審判などで実務家である弁護士の皆さんが経験される現実の家庭裁判所の機能ということを考えたときに、その実現可能性というのは本当にあるのかと。これは本当の大仕事じゃないかと。この法案の施行期間の間にそれが実現できるというふうな見通しをお持ちになれるかどうか、併せてちょっと、竹下先生、いかがでしょう。
○参考人(竹下博將君) まず、一点目の未成熟子のお話なんですけれども、なかなかこれは本人の能力だけで実は決めていないところもあるのではないかというふうに思っていまして、結局、大学に進学するということが許されるというのか、あるいはそうすべきというのか、そういうような環境にあれば未成熟子と考えてよいというような場合もあったりしますので、そうすると、本人の能力だけで本当に決めていいのかというところもあったりして、かなり曖昧な概念なのではないかなというふうに思っています。
結局、ここはケース・バイ・ケースで裁判所が判断していくところで、基準も分からないので、結局は未成年者になっているのが実態ではないのかなというふうに思っています。
二つ目の、養育費をアップデートにするとか、あるいは交通事故の例をというようなお話で実現可能性をということでしたが、私もそこは不思議に思っていまして、交通事故の場合は、保険会社が交渉するときの基準、代理人に弁護士が付いたときの交渉する基準、裁判所が最終的に判断する場合の金額、全部違っていることがあると思うんですけれども、今は全て同じなんですね、養育費については。
これはかなり乱暴だと思っていまして、裁判所が実際に判断をすることをかなりやめているのではないかと思っていまして、私も新算定表というものを日弁連で作るときに関わって、いろいろと様々な判断が裁判所でされているのを読んでいますけれども、正直、裁判所としてはこの問題に触れたくないのではないかなと感じているところです。論理的な批判を新算定表の提言ではしましたが、その批判に応えようとする理由というものを私はちょっとほとんど見たことがありません。誤解されているものはあったりはしますけれども。
したがって、そうすると、裁判所としてはかなり後ろ向きなんだと思っていたんですが、報道によれば、最高裁判所は司法研究としてこの点を研究すると、どうやら一年程度で研究をするということですので、変わる可能性は、実現可能性はそこで出てくるのかなというふうに思っているところです。
ただ、実際には、それが出れば、今の算定表にそれが取って代わるだけになるような気もしますので、柔軟に幾つかの基準を定めるという意味では、いろいろとこれからも日弁連としてもやっていくことであったりとか、行政が考えるというところもあるのかなとは思っています。
○仁比聡平君 氷海参考人、最後、ちょっと短いんですが、以前、法制審に平成二十年に御意見述べられたときに、正直言って民法を考えて高校の現場で教育はしていませんと、校則のことは考えるけれども、だけれども、民法のことを考えて教育はしていませんというお話をされているんですが、それは変わったという感じですか。
○参考人(氷海正行君) そのときの発言は、民法ってすごく深くたくさんいろいろな法律的なことがありますので、そこのところまで深く考えていないという意見ですね、それは。
やはり、民法の今の問いに関して、それよりも、あのときからもう十年たっていますので、随分と民法についてもいろいろと私の方も勉強というか耳に入ってきて考えていますので、考えていませんという話は、教育現場は常に民法を裏付けて教育はしていませんという言い方なんですね。したがって、考えていないというよりは、ちょっと誤解かもしれませんけれども、いろんな面で当然入ってきていますので、答えとしては、考えてはいますという答えになりますかね。
○仁比聡平君 ありがとうございました。
- 投稿タグ
- 憲法・人権